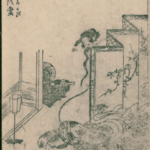美人画に革命を起こした喜多川歌麿の「大首絵」
蔦重をめぐる人物とキーワード㉝
■蔦重に見出された浮世絵界の巨匠
喜多川歌麿は、1753(宝暦3)年頃に生まれたとされる。出生地には江戸、川越、京都など諸説あるが、近年は江戸説が有力視されている。本名は北川信実(のぶざね)、通称は市太郎または勇助。幼少期より町狩野(まちかのう)派の鳥山石燕(とりやませきえん)に師事し、絵の修業を積んだ。
1775(安永4)年、富本浄瑠璃の表紙絵『四十八手恋所訳』を手がけ、浮世絵師としての第一歩を踏み出す。当初は「豊章」の画号を用い、勝川春章の影響を受けた役者絵を中心に制作していた。
1781(天明元)年頃、「歌麿」と改号し、画姓も「喜多川」と改める。この頃、版元・蔦屋重三郎と出会い、狂歌絵本『画本虫撰』『潮干のつと』『百千鳥狂歌合』などを次々と刊行。写実的な描写と文芸的センスが融合した作品群は高く評価され、歌麿の名声を確立する。
1791(寛政3)年、歌麿は美人画に「大首絵」という新しい形式を導入。従来の全身像に代わり、女性の半身を大胆にクローズアップし、表情や仕草を通じて内面を描き出した。大首絵は元来、人気絵師の勝川春章(しゅんしょう)・春好(しゅんこう)らが、役者絵で人気を博していた構図であったが、歌麿は美人画で採用。女性の表情を精緻に描き出し、新しい構図を実現した。
さらに、鉱物である雲母の粉末を用いて背景を摺り上げた雲母摺(きらずり)や、黄つぶしなどの技法を駆使し、色彩を節約しながらも印象的な美を表現。『婦女人相十品』『歌撰恋之部』『高名美人六家撰』『青楼十二時』などの傑作を生み出し、肖像画的な美人画の地平を切り開いた。
しかし、蔦重が1797(寛政9)年に没すると、歌麿の作風は変化を見せる。他の版元からの依頼が増えると多作・乱作の傾向が強まり、画技の低下が指摘された。晩年には肉感的描写が進み、退廃的な雰囲気が漂う作品が増加した。
1804(文化元)年、豊臣秀吉の正室らを描いた『太閤五妻洛東遊覧之図』が幕府の出版統制に触れ、手鎖の刑に処される。これは両手を縄で縛られたまま自宅謹慎を命じられる刑罰であり、絵師としての活動を大きく制限された。表現の自由を奪われた歌麿は、1806(文化3)年9月20日、失意のうちに54歳で没した。
歌麿が残した版画は2600点以上に及び、美人画の革新者として後世に多大な影響を与えた。式亭三馬(しきていさんば)は「女絵を新たに工夫する」と評し、フランスの文人エドモン・ゴンクールは「青楼画家」と称賛した。彼の作品は、江戸の空気を纏った〝生きた肖像〟として、今もなお人々を魅了し続けている。
- 1
- 2